日本山岳耐久レース(ハセツネCUP)は、東京都西部の山域で行われるレースです。
今年は世界選手権の選考レースになっていたり、ダブルの部が開催されたりと注目されています。
トレラン黎明期から多くのレジェンドランナーが出場してきた歴史と伝統のある大会です。
投稿者である私は、過去5回参加してこのような成績でした。
2014年第22回大会 8時間44分 24位 2015年第23回大会 8時間08分 7位 2016年第24回大会 8時間28分 6位 2017年第25回大会 リタイヤ 2018年第26回大会 9時間02分 7位
ハセツネにどのような戦略で臨んだかを解説します。参考になれば幸いです。
目次
時間配分

スタート→第一関門(浅間峠)→第二関門(月夜見)→第三関門(長尾平)→フィニッシュの時間配分は、
①スタート〜第一関門(浅間峠):2.5時間
②第一関門(浅間峠)〜第二関門(月夜見):2.5時間
③第二関門(月夜見)〜第三関門(長尾平):2時間
④第三関門(長尾平)〜フィニッシュ:1時間
という具合になります。
また、月夜見で分けると(①②+③④)=5時間+3時間です。
コースをシンプルに考えると、
①…小刻みなアップダウン
②…小刻みなアップダウン登り多め
③急登と激下り
④走れる下り
となります。
私は陸上あがりの、普段はロードで練習するランナーなので、
①ほどほどにがんばる
②耐えて力を温存
③登りは歩き、下りは捻挫しないように慎重に
④全開
という形がベストです。
自分の脚質に合わせて、どの区間でタイムを削り、どの区間は我慢するのか、戦略を立てて臨むと良いと思います。
順位を狙うか、記録を狙うか。
どちらか一つに絞る方が無難です。
順位を狙い過ぎると、前半の位置取りが気になってしまい、自分のペースを見失います。
順位でなく記録を狙う場合は、気温を考えます。
私の場合は、
15年大会:8時間08分
18年大会:9時間02分
で、どちらも7位です。
気温で1時間ほどゴールタイムに差がつきます。
気温が低いときは、脱水症状やエネルギー切れなどでリタイヤする選手が少なくなり、記録は狙えますが順位を上げることが難しくなります。
逆に高温になると、トラブルでリタイヤする選手が多くなり、自分がペース維持できているうちは勝手に順位が上がりますが記録はでません。
目安としては、スタート前の午前中の受付で、半袖で過ごせているときは、記録は狙えません。
スタート前の午前中に、半袖で“肌寒いな”と感じるときは、記録を狙うチャンスかと思います。
ハセツネに向けたトレーニング

10月の第2週に開催されるハセツネです。
夏のトレーニングの成果が発揮されるため、夏場に走り込む必要があります。
しかし、私の場合は、夏場の疲労が抜けきらずに本番を迎えてしまい、リタイヤしてしまった経験があります。
夏場のトレーニングは“ほどほど”が良いです。
具体的には、7~9月の猛暑の中で行うトレーニング1回あたりの距離は約4時間(45㎞)まで、それ以上の距離や時間を走る際は涼しい高地で行い、追い込むポイント練習は週2回まで、20㎞以上走るのは本番2週間前まで、などです。
2015年大会8時間08分7位への仕上げ方(ポイント練習のみ)
3週間前 OSJ小海100マイル:100㎞でリタイヤ 2週間前 平坦ロード40km走 pace4’30/km 1週間前 平坦ロード36㎞走 pace4’15/km
小海100マイルで山の刺激は十分に入れることができたと考え、2週間前からは距離に慣れることと疲労を抜くことを考えて山を走りませんでした。
残暑が厳しい年でしたので、ハセツネ前3週間を週1回のポイント練習のみとして、あとはjogでつなぎました。
無理しなくてよかったです。
2016年大会8時間28分6位への仕上げ方(ポイント練習のみ)
3週間前 トラック5000m公認記録会15分44秒 2週間前 ポイント練習①累積標高800m×2 38分+35分(登りタイム) ポイント練習②走れる山14㎞走 計80分 1週間前 ポイント練習①ロード30km走4’20/km ポイント練習②走れる山14㎞走 計80分 最終調整 トラック4000mペース走 3’35/km
この年は、仕事が忙しく時間が取れないこともあり“走れるときに走る”スタイルでした。
練習は、7月から月間走行距離200㎞を切っている状態でしたが、トラックの5000mのためにつけたスピードを、ロードの30㎞走をやることでハセツネ仕様に仕上げた形です。
ですからこの年は、ハセツネの結果はよかったもののその他のレースはボロボロでした。
やはり月間300㎞は練習しないと、ハセツネの距離を安定して走れる体にはならないようです。
2018年大会9時間02分7位への仕上げ方
3週間前 信越五岳110㎞完走第3位 2週間目 疲労から風邪をひいてしまい、jogできず ポイント練習 累積標高700m×2 45分+40分(登りタイム) 1週間前 ポイント練習 前週と同じ山×1 40分(登りタイム)
8月にハセツネ本コースの試走やTJARの応援で木曾駒ヶ岳往復15時間走など調子にのってやり過ぎてしまい、9月の信越五岳前には疲労がどっときてしまいました。
免疫力も下がり、信越五岳前後に風邪をこじらせました。
ハセツネ本戦は順位こそ7位にまとめましたが、攻めるレースはできませんでした。
前半から攻めていたらつぶれていたと思います。
夏場に無理をしない方がいいという教訓を得ることができました。
この教訓で翌2019年の信越五岳100マイルを優勝することができました。
ハセツネコース解説 スタート~第一関門浅間峠(約23㎞)

スタート後、位置取りのために自然とオーバーペースになってしまいますので注意を。
2㎞手前まで走れるロードなので走れ過ぎてしまいます。
失敗したレースは、ここでペースを上げ過ぎました。
心拍計をつけているなら、LT値よりも低い値を維持しなければなりません。
ちなみにLT値はハーフマラソンのペースなので、20㎞を全力で走るときの5km通過時の心拍数(150~155)と考えています。
呼吸は、“スースーハーハー”より少し速い“ハアハア”より上げません。
“ゼーゼー”までいくと上げ過ぎです。
ちなみに100マイルレースだと“ハーハー”になったらペースを落とします。
予定しているペースより上げると、筋や肝臓に貯めているグリコーゲン(糖質)が使われてしまい、すぐにエネルギー切れになります。
実際に自重せずにハイペースで突っ込んだ17年大会は、浅間峠前にも関わらず糖質切れのため、めまい、息切れ、吐き気などが起こりました。
ペースを抑えて自重すると渋滞に巻き込まれるかもしれません。
しかし、エネルギー切れを起こすとレース中に回復することは厳しいです。
グッと我慢して、心拍や呼吸と相談して入ることが肝要です。
スタートしてロードを下り、最初の登りがありますが、ここで息が“ハアハア”言っていることを自分自身が聞ける余裕があるかどうかを確認します。
そしてもう一度、今熊神社の階段の登りに入ってから、“自分の周りにいる選手たちよりも息遣いに余裕があるかどうか”を確認します。
ここでゼエゼエ言っていたら黄色信号。
ハアハアするくらいでペースを抑えておき、それ以上に呼吸・心拍が上がらないように注意します。
今熊神社の急登を過ぎるとハセツネ名物の小刻みなアップダウンが続きます。
下りはリラックスして刻みます。
下りでガンガン下ってしまうと、太ももの前(大腿四頭筋)や胃腸にダメージがくるので、脚や胃腸を労わりながら一歩を細かく刻んで衝撃を和らげながら進みます。
ただ、下り切る前に登りが見えてきたら、ギアをニュートラルに入れるイメージで惰性で下ります。
惰性でも下りなのでスピードは上がります。
そこで得たスピードを登りの最初に使うイメージです。
なので登りの最初は力を使わずに、下りで得たスピードだけで登ります。
次第に勢いを失い力を使って登り始めたら、パワーウォークに切り替えます。
よく「走らないの?」と聞かれますが、「レーストータルで走った方が速いなら走る」と考えています。
序盤は、テンションも上がっていてついついオーバーペースになりがちなので、登りはあえて歩くようにします。
登りでコンディションチェック

浅間峠までのいくつかの登りで、毎年コンディションのチェックをします。
長めの登りで、“戻されているな”と感じたら、ペースをあえて落とすようにします。
“登り坂に戻されている”は、いつもの感覚で登れていない証拠です。
逆に、後ろから押されているように勝手に足が進んでいく感覚があったら、タイムを削るためにペースを上げます。
ただしペースを上げるのは登りと平地のみで、下りはいつもと同じペースです。
ペースを上げるときは、パワーウォークを走りに切り替えることはしません。
ウォークのペースを上げるのみです。
“歩くところは歩き、平地は走る”で、どこか1か所だけ疲労することのないようにします。
ハセツネ序盤の特徴“階段”

スタートから三頭山までの登りは、階段が多いです。
階段がたくさんあるコースでトレーニングできていればいいのですが、そんな場所もないので、トレーニングの最後に階段ダッシュ40秒×5などを取り入れていました。
階段を何十往復するトレーニングはすべきなのでしょうが、飽きやすくいつでも止めて帰宅できてしまうので、やりませんでした。
その他に、本当はトレーニングの最後にバウンディングや片足ケンケン登り坂などやるべきです。
今、もしハセツネに向けてトレーニングするなら、毎日のジョグの後に、流し+バウンディング+ケンケンを取り入れてハセツネの階段の登りに負けない筋力をつけると思います。
もっていく水分

ハセツネは給水所が1か所なので、スタート時には水分を2リットルもっていきます。
内訳は、水で薄めたスポーツドリンクを1リットル、水を1リットル。
水切れしたときの予備としてOS-1ゼリーをザックに入れておきます。
毎年、月夜見手前5kmで飲み切るので、このゼリーは月夜見手前3㎞あたりで摂取することになります。
水は、水分補給以外にも、口をすすいだり手にかけたりして体温を下げるためにあるので、気温が高い年は計2.5リットルもっていきます。
もっていくエネルギー

ハセツネはエネルギー補給のためのエイドステーションがないため、スタート時に全部ザックに入れます。
塩分補給のタブレットを45分に1個、9時間完走として12個、予備3個、計15個。
エネルギーは、100マイルだと固形物を摂りますが、ハセツネは走るペースが速く、すぐにエネルギーになってほしいのでジェルとグミです。
45分ごとジェル1個+グミ1袋の半分、90分でジェル2個+グミ1袋です。
グミは噛んでいるのがつらくなる後半はジェルに置き換わります。
予備ジェル3個と合わせて、計ジェル15個、グミ3袋です。
トップスピードなどのアミノ酸は、1時間に1個が理想ですが、高価なので各パートに1個、計4個です。
胃腸に不安があるときは、ジェルの減らして食べ慣れたミニおにぎりをもっていきます。
塩を多くふりかけると食べやすくて喉を通ります。
ハセツネコース解説 第一関門浅間峠(約23㎞)~第二関門月夜見(約43㎞)

浅間峠は50位くらいで通過します。
リタイヤするランナーを含めるともっと後ろの順位で通過します。
それでも10位以内でゴールできるのですから、浅間峠以降のペース維持が大切だとわかります。
浅間峠で2時間30分前後なら8時間切りを狙えるので、記録を意識して走ります。
しかし最近のハセツネは暑いので浅間峠で3時間かかることもあります。
浅間峠手前でペースが遅いことはなんとなくわかるので、記録を追うことはあきらめ、ひたすら自分のできる範囲でのペースを維持に集中します。
途中、三頭山があります。後半に出てくる御前山、大岳山と合わせてハセツネの3大急登です。
絶対走りません。
欲をかかないようにします。
何度も書きますが、ここで脚を使ってしまうと後半走れません。
上半身と腕の筋力を補助にパワーウォークで脚を使うことを最小限にします。
急な登りでは、エネルギーと水分の補給を入れるなどして、“がんばらなきゃ”という気持ちにのめり込まないようにします。
開き直って“がんばって登っても急登がゆるくなるワケじゃないから休み休みいこう”そんな感じです。
しかし脚は止めずにいきます。
逆に言うと、脚を止めずにいられる、ゆっくりなスピードで登るということです。
唯一の給水、月夜見

ここでは1.5リットル、水かポカリを補給できます。
塩分と糖質がほしいので最初の300mlはポカリを飲みます。
あとは、エネルギーが足らなさそうであればポカリを多めハイドレに入れてもらいます。
ジェルの残りに心配がなければ、ハイドレは水にします。
前述した通り、手や首筋に水をかけて体を冷やすためです。
ハセツネコース解説 第二関門月夜見(約42㎞)→第三関門長尾平(約60㎞)

スタートから浅間峠までの区間タイム①と、浅間峠から月夜見までの区間タイム②をおおよそ計算して、①に比べて②で大幅に遅れていなければペースメイクはばっちりです。
もし②で①より時間が大幅にかかっているようであれば、この先の御前山や大岳山の急登で止まってしまうかもしれません。
そうならないように、月夜見で大休憩をとるのもいいでしょう。
ペースメイクがうまくいったときは、ここからゴールまで多くの選手を抜くことになります。
1kmごとに1人以上が目安です。
こうなってくると前の選手の明かりを目標にしていけますから、ミスコースも心配なくプッシュしていけます。
また、月夜見で水分1.5リットルを補給できれば、自然水がある綾広の滝(御岳山手前1.5㎞)、御岳神社までガンガン使えますし、夜間になって気温も下がりますので、体も楽に感じます。
御前山を過ぎた大ダワの下りは、石段の幅が大きく、ダメージを受けますし石が滑りやすいので慎重に進みます。
プッシュするのは、なだらかな平地です。
特に大岳山を過ぎてから長尾平までは、走れる区間が続きます。
道もはっきりしているので最終区間のスパートに向けたウォーミングアップのように徐々にペースを上げていきます。
ハセツネコース解説 第三関門長尾平(約60㎞)→フィニッシュ(約71.5㎞)

長尾平の手前から走れる区間です。
勢いそのままに、長尾平の関門を走り抜けます。
走れるといつの間にかエネルギー切れになっていることがあるので、エネルギー補給を忘れずにします。
残りのジェルに余裕があれば、予備1個を残して長尾平手前までに摂取してしまいます。
長尾平からフィニッシュまで走ると60分を切るので、水だけあれば大丈夫となります。
ジェルを食べてしまえば荷物も軽くなるので、コースも荷物も気温も一番走れる状態になります。
ここでしっかりと走るために、これまでレースを組み立ててきたと言えます。
私は、下りが得意なダウンヒラーでもスカイランナーでもありません。
最終区間は、テクニックが必要のない下りです。
走れる脚とエネルギーさえ残しておけば、だれでも颯爽と駆け抜けていけるのではないでしょうか。
地図通りだと11.5㎞ありますが、GPSだと9kmほどです。
平坦なロードで走る感覚からプラス1分が、この区間のペースになります。
平坦なロードで3’50/kmのがんばり具合だと、この区間ではだいたい4’50/kmになります。
この最終区間で過去3回、60分を切っていますが、全部走れたわけではありません。
ちょっとした登りではパワーウォークでしのいで、走れるところをしっかり走りました。
走っても歩いてもペースが変わらなければ、迷わず歩くことを選択します。
そうする方がトータルで考えると速くなります。
まとめ

私ほど前半を慎重にいくことは珍しいかもしれません。
しかし、ハセツネ本戦の距離71.5㎞を仮にアップダウンのあるロードで走ってみたらどれほどのペースで完走できるでしょうか。
もちろん、レース同様の装備(ザック約4㎏)を背負ってです。
私なら、4’20~4’30/kmほどのペースがイメージできます。
ザックを背負って4’30/kmで走るとすると、心拍数はだいたい140前後になります。
この心拍でハセツネコースを走ると、上記のようなレースプランとなります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
是非ハセツネを楽しんでください!
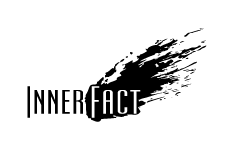

コメント